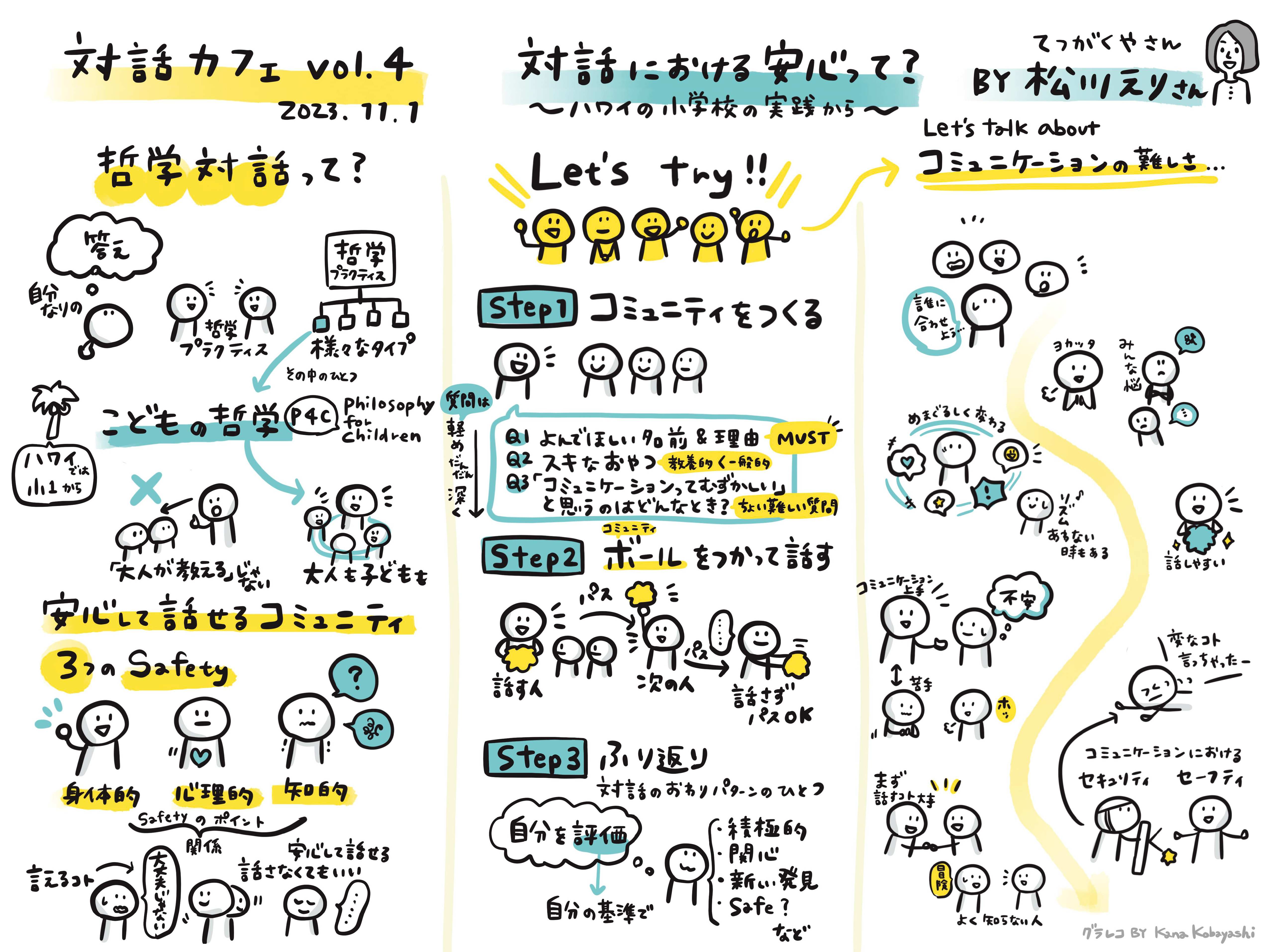
対話カフェ Vol.4
テーマ:対話における安心って?~ハワイの小学校の実践から~
2023年11月1日、エキマエノマエで「対話における安心って?~ハワイの小学校の実践から~」をテーマに対話カフェが開催されました。
今回は13名の参加者が集まり、みんなで「対話における安心」について学びました。
対話カフェのルール
- 何を言ってもいい
- 人の意見を否定しない
- 発言せずに聞いているだけでもOK
- 知識ではなく、自分の経験に基づいて話す
- 話がまとまらなくても大丈夫
ハワイの小学校の実践
ゲストファシリテーターの松川えり先生(NPO法人だっぴ代表理事)による講演が行われました。
- 哲学者には3タイプ「研究者・文筆家・実践者」があり、自分は実践者である。
- その実践を、「哲学対話」という手法で行っている。
- ママさんの集まる場や年配の方が集まる場、ホスピスの場や市議会議員が市民と交流する場、小学校や高校の学校現場などで実践してきた。
- 哲学とは、正解が決まっていない問題について、自分自身の答えを探究する営みである。
- 特にコミュニケーションを介して行う哲学が「哲学プラクティス」と呼ばれる。
- ハワイの小学校でも「哲学対話」を取り入れている。
- 背景や文化が異なる子どもたちが集まるハワイの学校現場では、合意形成や価値観の違いを認めるために「哲学対話」が重要。
- 子どもでも参加しやすいハワイ式の「対話の場」が、共生社会の実現に向けて相性が良い。
- ファシリテーターにかかる負担が少なく、比較的誰でも難しくなくファシリテーターができる。
- 最も大切なのが「Safe Community of Inquiry」、つまり安心して話せるコミュニティ。
- セキュリティとセーフティの違い。セーフティとは「大丈夫、大丈夫」と言える環境。
- ファシリテーターの役割は、助け合ってケアできる雰囲気を作ること。
哲学対話の実践
参加者は自己紹介をしながら、コミュニティボールを制作しました。
- コミュニティボールとは、それを持っている者だけが話す権利を持つアイテム。
- 自己紹介では、よんでほしい名前、好きなおやつ、コミュニケーションの難しさについて話しました。
- これにより、安心感を与えるために少し弱みを共有しました。
哲学対話のルール
対話の実践では以下のルールが適用されました。
- コミュニティボールを持っている人だけが話せる。
- 話し終えたら、手を挙げた人にコミュニティボールを渡す。
- 複数人いた場合は、話し手が選ぶ。
- 手を挙げる人がいなかったら、次に話す人を選ぶこともできる。
テーマは「なぜコミュニケーションは難しいか」でした。
- 人によってスイッチの切り替えが必要で、複数人とのコミュニケーションになると難しい。
- 複数人で話すのは難しい。
- 他の人と同じ考えを持つことで安心感を得る。
- 輪の中のテンポについていけない。
- 仕事柄、人間関係の調整が難しい。
- この場は、相手のことを話してみないとわからない場である。
- コミュニケーションの難しさには、戦争のトラウマが影響しているかもしれない。
- コミュニケーションが得意な人がいても、不安になることがある。
- コミュニケーションが苦手な人に、ほっとすることもある。
ハワイ式対話のデメリット
- 進行役のコントロールが効かない(メリットでもある)。
- ずっとコミュニティボールを持っている人がいる。
- 学校では男子だけがコミュニティボールを持っていることが多い。
ハワイ式対話のファシリテートについて
- 主題から外れた場合、そのままにしておくのも方法。
- 元のテーマに戻りたい場合は、正直に伝える。
- 差別的な意見が出た場合は、ボールを預かり全体に意見を求める。
- 口論を防ぐと、誰かが我慢していることになる。
みんなの感想
最後に参加者たちから感想が述べられました。
「相手のことは話してみないとわからない。この場はそれができる場であると思う」
「コミュニケーションの難しさには、戦争のトラウマがあるのではないか」
「哲学対話のデメリットも含めて、非常に有意義な時間だった」
おわりに
今回の対話カフェでは、「対話における安心」というテーマについて多くの視点から対話がおこなわれました。
次回の対話カフェも楽しみにしています!



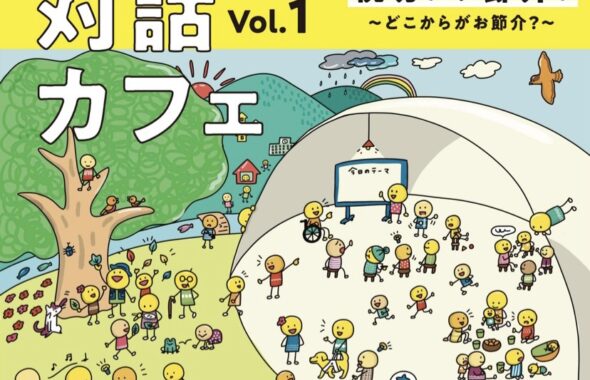
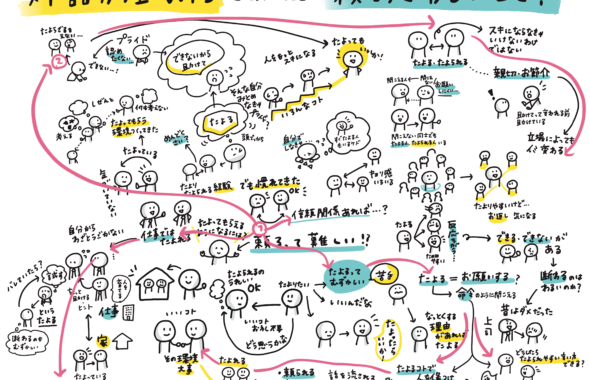


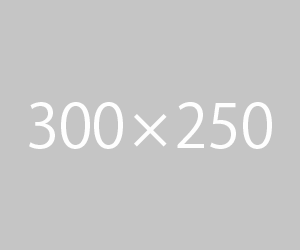
この記事へのコメントはありません。